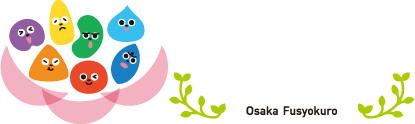府職労・病院労組は3月13日、病院機構と団体交渉を行いました。オンラインも含め18人が参加し、各病院・病棟の実態を訴えました。その結果、3月17日にはボーナスの引上げなどの回答が示されました。
「経営環境」を理由に給料引上げは見送り
病院機構は、基本給の改定について「国立病院機構が改定を行わないと決定した」「病院機構の経営環境は極めて厳しく、独自に基本給を引き上げることは難しい」と、給料引上げを見送ると回答しました。その一方で、「期末・勤勉手当(ボーナス)については年間0・1月分を引上げ、4・6月分とする(※)」と回答しました。また、住居手当について再雇用職員も対象とすると回答しました。
実施時期については「いずれも令和7年度から適用する」としています。
※再雇用職員及び定年前再雇用短時間勤務職員:年間0.05月分引上げ、年2.4月分
※非常勤職員:期末加算額の支給対象者を勤務時間が1週当たり15.5時間以上に拡大、年間0.025月分引上げ、年1.475月分
これに対し府職労・病院労組は、「物価高騰が続く中、基本給が据え置かれれば、職員の生活はますます厳しくなる」「この状況では人材確保が難しくなり、離職・転職を助長する可能性もある」と厳しく追及しました。
病院機構は「病院職場は人なくして成り立たない。優秀な人材を確保し、定着してもらうことは重要だ」と述べる一方で「経営状況を考慮すると苦渋の選択をせざるを得なかった」と説明しました。
また、ボーナスの引上げについて、府職労・病院労組は「基本給を国立病院機構に準じるというのであれば、ボーナスは大阪府に準じて4月に遡って引上げるべきではないか」と強く追及しました。これに対し病院機構は「手当は府に準じるというルールについては重く受け止めている。その結果、厳しい経営状況の中でも引上げを決定した」と述べました。
府職労・病院労組は「このままでは毎年1年遅れの引上げとなる」と追及し、大阪府と同時期に引上げるよう求めました。病院機構は「今後の検討課題の一つとして考えている」と一定の前向きな姿勢を示しました。
府職労は、子育て部分休暇の対象年齢引上げについても追及。病院機構は「前向きに検討したい」と回答しました。
年休の希望制限や拒否は問題あり
交渉では指定休を正しく付与しない、年休の希望を拒否や日数を制限は、本来あってはならないことであると確認し、各病院・病棟に周知徹底するよう求めました。また、「そもそも休暇が希望どおり取れない背景には、慢性的な人手不足がある。抜本的な解決策として、人員配置の改善が必要だ」と、休暇が希望どおり取れるよう人の配置も強く求めました。
このままでは患者の安全が守れない
交渉の最後に、府職労・病院労組の山本委員長は「到底納得できる内容ではない。これでは医療スタッフは現場で安心して働き続けることはできない」「人の命を預かる現場で働く私たちが、なぜこれほど劣悪な待遇を強いられ続けなければならないのか。もう我慢の限界だ」と抗議するとともに、「この状況を放置すれば、より多くの人材が流出し、現場はさらに疲弊し、患者の安全も守れなくなる」と指摘しました。そのうえで、「大阪府健康医療部への申入れも含め、引き続き要求を提出し、交渉を継続する」と表明しました。
今回の交渉を通じて、これまでの「ゼロ回答」を変更させ、ボーナス引上げの回答を得ることができましたが不十分です。
府職労・病院労組は今後も、職員の処遇改善をめざし、病院機構および大阪府に対し、さらなる働きかけを続けていきます。